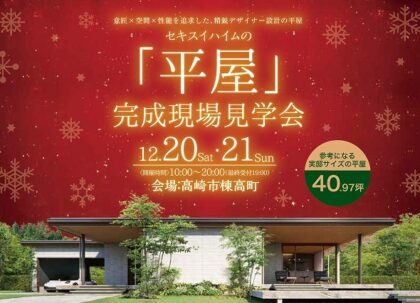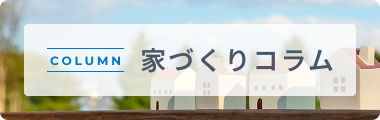住宅を購入する際に「セットバック」という言葉に戸惑いを覚える人は多いでしょう。なぜ必要なのかを正しく理解していないと、購入後に思わぬコストが発生してしまい、建築計画に影響を及ぼす可能性があります。
この記事では、概要から必要な理由や計算方法、購入時に気をつけたいポイントまでを解説します。また、該当する物件を購入しても問題ないケースや購入後に行うべき手続きについても紹介します。
セットバックとは
土地や建物を敷地の内側に下げて配置し、道路の幅を広げるために行われる措置をセットバックといいます。もともとは英語の「set back(後退する)」に由来する言葉です。
建築の計画を立てる際に、道路と敷地の境界線から一定の距離を空けることを意味します。ここからは、必要な理由と計算方法について解説します。
セットバックが必要な理由
敷地が幅4m以上、地域によっては6m以上の道路に2m以 上接していなければ建物を建築できないと定められています。このような規定は、災害時に消防車や救急車がスムーズに通行できるようにするためのものです。
しかし、古い時代に整備された道のなかには幅が不足しているものも多く、すべての道路を一度に拡張するのは現実的ではありません。そのため、建て替えや新築の際に敷地を後退させて、将来的に十分な道路幅を確保するために考えられました。
必要になるのが、幅が4m未満の道路に面しており、建築基準法の施行以前から建物が存在していた土地です。特定行政庁の指定を受けたこうした道路は、2項道路と呼ばれます。
2項道路は、正式な道路と同じ扱いを受ける代わりに、建築時には敷地の一部を道路拡張に協力することが求められています。
引用元:デジタル庁| e-Gov 法令検索「建築基準法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201)
セットバックの計算方法
計算方法には、以下の2通りがあります。それぞれの計算方法について解説します。
道路の向かい側が宅地の場合
住宅が建ち並んでいる場合は、それぞれの土地所有者が協力する必要があります。具体的には、道路の中央を基準にして、それぞれの敷地を道路の中心線から2m以 上後退させることが求められます。
双方の協力によって、道路全体の幅を将来的に4m以上確保できる仕組みです。たとえば、現在の道路幅が2.5mである場合、両側の土地をそれぞれ0.75mずつ後退させることで、必要な幅を満たすことが可能となります。
この措置は、建て替えや新築工事を実施する際に義務づけられています。すでにある道路幅が基準を満たしていないエリアでは、将来的なまちづくりに向けて欠かせない取り組みです。
この仕組みによって、緊急車両が安全に通行できる道幅を確保し、地域の防災力を高めることにもつながるでしょう。
道路の向かい側が川・崖・線路の場合
道路の向かい側に建築ができない地形が存在する場合は、反対側から必要なスペースを確保するのが難しくなるでしょう。このような場合では、すべて自分の土地で対応しなければなりません。
具体的には、道路境界線から水平距離で4mを 確保することが義務づけられています。たとえば、現状の道路幅が3.5mであれば、不足分の0.5mを自分の敷地から下げて対応することになります。
しかし、みずからの土地を後退させたとしても、川や崖などの障害物があって4m以上の幅員が確保できない場合も考えられるでしょう。このような状況では、原則として建築が認められません。
したがって、建物の新築や建て替えを計画する際には、事前に慎重に確認するようにしましょう。道路拡幅に協力する責任を負う点を十分に理解しておく必要があります。
セットバック物件を購入する際の注意点
以下の5つに注意しましょう。
● 防災性や利便性が低くなる
● 敷地面積が小さくなる
● 利用上の制限を受ける
● セットバックの工事費用が発生する
● 売却しづらくなる可能性がある
それぞれのポイントについて解説します。
防災性や利便性が低くなる
幅が4m未満の道路に接しているケースが多く、防災面で不安が残るといえます。緊急車両の通行スペースを確保するために設けられた接道義務を満たしていないため、火災や救急時に支障をきたすリスクが高まります。
とくに、幅の狭い2項道路に面する物件では、火災時の消火活動や救急搬送が遅れるおそれが否めません。また、一般の車両も通行しづらいため、買い物や通勤といった日常生活でも不便さを感じる可能性があります。
建て替えを前提に購入する場合を除き、セットバック未対応のまま長期間居住することは、生活の安全性や利便性に影響を及ぼすリスクが伴います。あらかじめ認識しておくことが必要です。
敷地面積が小さくなる
後退した部分は事実上、道路の一部として扱われるため、建物を建て替えられなくなります。その結果、有効に利用できる敷地面積が小さくなり、建築できる建物の大きさにも影響が及ぶ点には注意しなければなりません。
土地の利用に関しては、地域ごとに建ぺい率や容積率が定められており、建物の面積や延べ床面積には厳格な制限があります。措置が求められる土地では、設計できる建物の規模が当初の想定より小さくなるでしょう。
たとえば、もともと150㎡あった土地がセットバックによって130㎡に減少した場合、建築できる建物の面積もそれに応じて縮小されます。購入前には、有効面積を正確に把握し、希望する建物が建てられるかを慎重に検討することが重要です。
利用上の制限を受ける
所有権が残るものの、法律上は道路とみなされるため、利用に厳しい制限が課されます。セットバックした箇所には何かを建てられないだけでなく、門などを設置したり、物置として活用したりすることも認められていません。
仮に、私的な目的で使用すると、建築基準法に違反する可能性があるため注意が必要です。門や塀、駐車場などを設置したい場合は、残るスペースを基準に計画を立てる必要があります。
とくに、土地の形状や広さによっては、想定していた設置が難しくなるケースも考えられるでしょう。そのため、事前に十分な検討を行わなければなりません。土地活用について誤解がないように、購入前にしっかりと確認しましょう。
セットバックの工事費用が発生する
該当する土地を購入すると、後退作業に伴う費用が発生することを念頭に置く必要があります。具体的には、土地の正確な位置を確定するための測量費用や、道路として整備するための舗装費用などが挙げられます。
また、敷地に高低差がある場合や既存の塀や構造物がある場合には、撤去や整備のために別途コストがかかるケースも少なくありません。加えて、宅地と道路を明確に分けるためには、分筆登記が必要となり、その登記費用も自己負担となるのが一般的です。
工事にかかる金額は、それぞれの状況によって異なります。そのため、購入前に見積もりを取るようにしましょう。
なお、自治体によっては一部費用の補助制度を設けている場合もあります。必要に応じて、事前に確認しておくと、負担を軽減できる可能性があります。
売却しづらくなる可能性がある
一般の物件に比べて、売却が難しくなる傾向にあります。建て替える際には、利用できる土地の面積が減ってしまうため、買い手にとって魅力が薄れることが主な理由です。
また、後退した部分には設備などを設置できない点も、購入されづらくなる理由のひとつとして挙げられます。資産価値も目減りすると判断されやすいです。
その結果、仮に売却できたとしても、取引価格は周辺相場より低く抑えられる可能性が高まります。そのため、将来的に売却を視野に入れる場合は、購入時にどのようにして手放すのかを慎重に考慮することが不可欠です。
建物の解体後に売り出す、もしくはセットバックに要する費用を考慮して価格設定するなど、あらかじめ対応策を検討するとよいでしょう。家族に相続させる予定がある場合であっても、購入前にしっかりと意向を確認しておくことが重要です。
セットバック物件を購入してもよいケース
購入してもよいケースは、以下の3つです。
● 価格が安い場合
● 敷地面積が小さくても許容できる場合
● 建て替えや売却の予定がない場合
それぞれのケースについて解説します。
価格が安い場合
セットバックが求められる土地は、一般的に周辺相場と比べて価格が低く設定される傾向にあります。後退した部分が建物を建てられないスペースとなるため、実質的に利用できる敷地面積が減少し、土地の価値が目減りするためです。
ただし、セットバック後の有効面積をもとに坪単価を見直した場合であっても、相場より安価に購入できるのであれば、十分に検討する価値があります。とくに、地価が高騰しているエリアで予算を抑えたいと考えている場合、有効に働くでしょう。
ただし、セットバックに必要な測量費用や整備費用は、原則として購入者が負担する必要がある点には、注意しなければなりません。こうしたコストも含めたうえで、本当にお得かどうか慎重に見極めることがポイントです。トータルコストを踏まえ、検討しましょう。
敷地面積が小さくても許容できる場合
セットバックによって敷地面積が減少すると、建物の規模に制限が生じて、思い描いていたプランを変更せざるを得ない可能性があります。
しかし、もともと敷地に余裕があり、セットバック後でも必要十分な面積を確保できる場合は、家づくりに支障は出ないでしょう。
また、敷地が多少狭くなったとしても、希望する生活スタイルに合致し、利便性の高いエリアに位置しているのであれば、後悔のリスクは低くなります。立地や周辺環境が希望に添うのであれば、多少の敷地面積の減少は受け入れられると判断できる場合もあるでしょう。
購入前にはセットバック後の有効面積を正確に把握して、自身や家族にとって本当に満足できる住まいを実現できるか慎重に検討することが大切です。
建て替えや売却の予定がない場合
セットバックが求められる土地は通常、幅が狭い2項道路に接しています。しかし、現状の建物をそのまま使用し続ける限り、セットバックを実施する義務は発生しないため、建て替えや売却の予定がない場合はとくに問題を感じずに済むでしょう。
中古物件として購入し、長期にわたって居住することを前提とするのであれば、セットバックに伴う費用負担や敷地縮小のリスクを心配する必要はほとんどありません。ただし、防災面ではリスクが残ります。
万が一に備えて、リフォームや補強工事などで安全性を高める対策を講じることが望ましいでしょう。将来的に自宅として使い続ける場合も、賃貸物件として運用する場合も、安全を最優先に考えた判断が求められます。防災性を無視して放置することは避けたほうが無難です。
セットバック物件を購入した後にすること
すべきことは、以下の2つです。
● 固定資産税の非課税申告をする
● 寄付や買い取りが可能か自治体に確認する
それぞれ解説します。
固定資産税の非課税申告をする
不動産を所有すると、毎年固定資産税や都市計画税の支払い義務が生じます。しかし、セットバックにより後退した部分は道路予定地とみなされるため、課税対象から外れる扱いとなります。つまり、該当部分は、固定資産税や都市計画税の負担が不要になる可能性があります。
ただし、非課税の適用を受けるには、みずから自治体に申請する必要があります。具体的には、非課税適用申告書に加えて、土地の登記事項証明書やセットバック部分を示した測量図などを提出しなければなりません。
役所から案内が届くわけではないため、購入後は忘れずに手続きを進めましょう。適切な申告を怠ると、本来支払う必要のない税金を負担し続けることにもなりかねません。そのため、できるだけ早めの対応を心がけましょう。
寄付や買い取りが可能か自治体に確認する
セットバックを行った土地の一部は、道路用地として公の役割を担うことになりますが、所有権は引き続き個人に残ります。そのため、原則として管理や維持は所有者の責任となり、思わぬ負担となるケースも考えられるでしょう。
負担を軽減する方法として、自治体へ寄付が考えられます。ただし、セットバック部分は地域の安全確保を目的とした制度にもとづくものであり、基本的には無償提供、つまり寄付を求められるケースが一般的で、一定の条件を満たしている必要があります
自治体によっては、例外的に買い取りや一定の助成金を支給する制度を設けている場合もあります。購入後は、必ず建築指導課や都市計画課などの担当窓口に相談して、寄付や買い取りの可否、手続き方法について確認しましょう。
セットバックに関するQ&A
以下では、よくある質問3つに回答します。それぞれ確認しておきましょう。
セットバックしないと罰則はある?
セットバックのルールに従わず、建物を建築した場合は建築基準法違反とみなされ、是正命令や罰金といった法的措置を受ける可能性があります。違反が認められた場合は、建物の使用停止や改修命令が下されるケースも少なくありません。
そのため、土地を購入する際は、対象地にセットバックの必要性があるかどうかを不動産会社や自治体に必ず確認しましょう。加えて、事前に適切な対策を講じることも欠かせません。
建築に関連したトラブルを未然に防ぐためにも、計画の段階から慎重な確認作業を心がけましょう。
セットバック部分は駐車場として利用できる?
セットバックによって後退した土地は、原則として道路とみなされるため、私的な使用は認められていません。したがって、駐車場として利用することも、本来は許されない取り扱いとなっています。
しかし、現実には車両や歩行者の通行を妨げない範囲で、駐車スペースの一部として活用している例も少なくありません。一方、このような使用は周囲に迷惑をかけるリスクを伴います。
たとえば「通行の妨げになる」や「一部の住民だけが得をしている」といった苦情が寄せられる原因にもなるでしょう。近隣住民とのトラブルを防ぐためにも、セットバック部分を駐車場に転用することは控えたほうが無難です。
また、セットバックした部分には住宅や倉庫、ガレージなど、いかなる構造物も建築することが禁じられています。誤解を避けるためにも、ルールをしっかりと把握しておきましょう。
セットバック済かどうか確認するには?
確認方法としては、測量士などの専門家による現地測量を依頼し、道路中心線からの距離を調べる方法があります。また、周囲の建物の配置や境界線の状況から、おおよその判断ができる場合もあります。確実なのは、役所に問い合わせることです。
管轄の建築指導課や道路管理課に確認すれば、公式な資料や図面をもとに、セットバックの有無や必要な後退距離を明確に把握できます。
万が一、未対応であった場合には建築や売却に支障が出る可能性もあるため、早めに正確な情報を確認しましょう。
まとめ
セットバックとは、道路の拡幅に対応するため敷地を後退させる措置であり、住宅購入に際して重要な判断材料のひとつです。道路幅や敷地面積に制限が生じること、防災性や資産価値に影響を与える可能性があるため、慎重に検討することが欠かせません。
セットバック物件を選ぶ際には、価格や有効面積、将来の建て替え計画なども踏まえた判断が求められます。大切な資産となる住まい選びを失敗しないためにも、安心して依頼できるハウスメーカーを選びましょう。
住まいの性能や品質にもこだわりたい方は、ぜひ群馬セキスイハイムにご相談ください。工場生産による高精度住宅と60年サポートシステムで、一生ものの安心と快適を得られる住まいをお届けいたします。
販売から施工、アフターサポートまで一貫体制で対応しているため、住まいづくりの不安や疑問も安心してご相談いただけます。末永く心地よい暮らしをかなえるために、群馬セキスイハイムに一度ご相談ください。