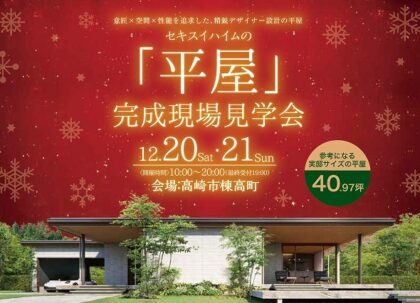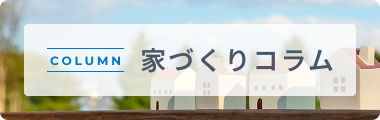マイホームを購入する際、多くの人が目安にしているのが年収です。しかし、年収がいくら以上であれば、マイホームを購入できるのか悩んでいる方も少なくありません。
この記事では、年収を踏まえてどの程度のマイホームを購入すべきかを考えるうえで重要なポイントについて解説します。マイホームを購入する際に多くの人が利用する住宅ローンや年収以外で考慮すべきポイントについても解説しますので、参考にしてください。
- 目次
マイホーム購入時の年収の目安は?
マイホームを購入する際、以下の値を目安にするとよいでしょう。
● 世帯年収と年収倍率
● 初めてマイホームを建てた人の平均世帯年収
それぞれの値について解説します。
世帯年収と年収倍率
マイホームの予算を算出するにあたって、用いられる指標のひとつが「年収倍率」です。年収倍率は、年収に対して住宅の購入価格がどの程度の割合を占めるのかを示しており、住宅購入における判断材料となります。
具体的には、購入予定の物件価格を年収で割った値が年収倍率です。たとえば、年収400万円の人が2,800万円の住宅を購入した場合、年収倍率は7倍となります。
2023年に住宅金融公庫「フラット35利用者調査」を利用して注文住宅を建てた人の年収倍率は、全国平均で約7倍であることを公表しました。したがって、7倍前後をひとつの目安にできます。
また、年収倍率は地域でも異なり、首都圏では7.2倍、群馬県では6.5倍程度です。値に違いが出るのは、地域によって住宅価格が異なるためであり、とくに都市部では物件価格が高くなる傾向があります。
しかし、年収倍率が7倍という数値だけで判断するのは、リスクがあることを認識する必要があります。仮に年収が同じであっても、家族構成やライフスタイルによって生活費は異なるためです。
たとえば、世帯年収が600万円の夫婦二人の世帯と、同年収の4人家族の世帯では、日々の支出がまったく変わります。家族の状況や今後の支出も考慮しながら、無理のない予算を設定しなければなりません。
つまり、年収倍率はマイホームを計画する際のひとつの参考値に過ぎないのです。家計に適した予算を考える際には、その他の要素もバランスよく見極めることが欠かせません。
初めてマイホームを建てた人の平均世帯年収
初めて住宅を建設する世帯の年収は、年代や地域によって異なります。国土交通省の「令和5年度住宅市場動向調査」によると、40歳未満の世帯では約746万円、40代では946万円、50代では943万円、60歳以上では763万円が平均年収です。
一方、三大都市圏では、同年代の平均年収がさらに高い傾向にあります。具体的には、40歳未満で857万円、40代で1,067万円、50代で1,027万円、60歳以上で926万円に達しました。
全国的に見れば、世帯年収のなかで最も多いのは、600万円以上800万円未満の範囲です。全体の22.2%を占めています。
それに対し、都市部では800万円以上1,000万円未満が主流となり、20.8%を記録しています。なお、群馬県の平均年収は550.3万円です。
一方で、初めてマイホームを購入する世帯のうち、約13.4%は年収400万円未満で住宅を建てています。必ずしも高い年収がマイホーム取得の条件ではなく、うまく資金計画を立てられれば、平均年収以下でもマイホームを建てることは可能であるといえるでしょう。
年収だけにとらわれず、自身の状況に合った適切な計画を進めることが重要です。
マイホームと住宅ローン
マイホームの購入と住宅ローンについて本格的に考える際、まずは以下2つの項目についての理解を深める必要があります。
● 返済負担率
● 返済負担率の目安
それぞれの項目について解説します。
返済負担率
住宅ローンを組む際、購入者がきちんと確認すべき指標のひとつが「返済負担率」です。返済負担率とは、年収に対して住宅ローンの年間返済額がどの程度の割合を占めているかを示す数値を指します。
返済負担率が高くなればなるほど、生活費や将来の支出に影響が出る可能性が高くなるため、しっかりとした計画が必要です。返済負担率は、以下の計算式で求められます。
返済負担率=年間ローン返済額÷年収×100
たとえば、年収550万円の人が年間120万円のローンを返済する場合、返済負担率は約22%となります。返済負担率は、金融機関が住宅ローンの審査時にとくに重視する要素で、一般的な上限は30~35%程度です。
ただし、30~35%の範囲はあくまで借入可能額の目安であり、返済が無理なくできる範囲かどうかは別の問題です。実際に、病気や失業などの予期せぬ状況が発生した場合、返済の負担が大きくなるリスクがあります。
子どもの進学や老後の生活資金などを考慮すると、返済負担率は低いほど安心できるでしょう。
返済負担率の目安
無理のない返済負担率として、20~25%程度を目安することがおすすめです。目安を超えると、生活費や予期せぬ出費に対応する余裕がなくなり、家計に大きな負担がかかる可能性があります。
2023年の「フラット35利用者調査」では、全国平均の返済負担率は25.6%、群馬県では24.3%であることが公表されています。いずれも、目安にすべき20~25%程度です。
実際に、年収ごとに借入額の目安をシミュレーションすると、以下の表のようになります。設定した条件は、金利が1.820%、借入期間は35年、元利均等でボーナス返済はなしです。また、借入額の右隣に返済負担率25%に設定した際の年間返済額も記載しています。
| 年収 | 借入額 | 年間ローン返済額(返済負担率25%) |
|---|---|---|
| 300万円 | 約2,328万円 | 75万円 |
| 400万円 | 約3,622万円 | 100万円 |
| 500万円 | 約4,527万円 | 125万円 |
| 600万円 | 約5,433万円 | 150万円 |
| 700万円 | 約6,338万円 | 175万円 |
シミュレーション結果を踏まえて年収に応じた適切な借入額を設定すると、無理なくマイホームを持てるでしょう。無理のない返済計画を立てるためには、返済負担率を意識しながら、自身の生活費や将来の支出も考慮して、慎重に資金計画を進めることが重要です。
年収以外で考慮するポイント
年収のほかにも、以下のポイントを考慮する必要があります。
● 頭金と貯金額
● 現金払いが必要な諸費用
● ローン完済時の年齢
それぞれのポイントについて解説します。
頭金と貯金額
住宅を購入する際、頭金の金額は重要な要素のひとつです。頭金を多く入れると借入額が減り、将来的な返済負担や利息を抑えられます。しかし、貯金のバランスを保つのも欠かせません。
マイホーム購入は、手元資金をすべて使い切らないことがポイントです。予期せぬトラブルや出費に備えるため、最低でも半年分の生活費を確保しておくと安心できるでしょう。
また、住宅購入時に発生する諸費用も頭金とは別に準備しておく必要があります。諸費用は現金での支払いが求められる場合が多く、足りないと追加の借り入れが必要になるため、注意が必要です。
現金払いが必要な諸費用
実際に現金払いしなければならないのは、以下の諸費用です。
● 物件にかかる諸費用
● 住宅ローンにかかる諸費用
● 諸費用にかかる目安
それぞれの費用に関する詳細と金額の目安を解説します。
物件にかかる諸費用
マイホームを購入する際には、物件そのものの価格のほか、さまざまな諸費用を現金で支払う必要があります。たとえば、以下の費用が挙げられます。
● 印紙税
● 不動産取得税
● 登録免許税
● 司法書士への報酬
● 固定資産税清算金
● 修繕積立基金
● 仲介手数料
印紙税は売買契約書に必要な税金で、不動産取得税は土地や建物の取得にかかる地方税です。また、所有権を正式に登記する際には登録免許税がかかります。手続きは司法書士に依頼するケースが一般的で、その費用も支払わなければなりません。
固定資産税や都市計画税の清算金も購入時に発生し、中古物件では修繕積立基金もかかります。さらに、不動産会社に仲介を依頼した場合は、仲介手数料も加わります。こうした諸費用を事前に把握し、資金計画を立てておくことが重要です。
住宅ローンにかかる諸費用
住宅ローンを組む際、物件価格だけでなく、いくつかの諸費用が発生します。代表的な費用は、以下のとおりです。
● 印紙税
● 登録免許税
● 司法書士への報酬
● 融資事務手数料
● ローン保証料
● 物件調査手数料
● 火災保険料(および地震保険料)
印紙税は、住宅ローン契約書にかかる税金です。登録免許税は、金融機関が抵当権を設定する際に必要な費用で、司法書士が手続きを代行する場合は報酬が発生します。
さらに、融資事務手数料やローン保証料、物件調査手数料も考慮に入れなければなりません。ローン契約時には火災保険への加入が必須となっており、地震保険も任意で追加できます。こうした費用は住宅購入時に発生するため、あらかじめ準備しておくことが大切です。
諸費用にかかる目安
主な諸費用の金額の目安は、以下のとおりです。
● 印紙税:2~4万円程度
● 不動産取得税:固定資産税評価額の3%程度
● 登録免許税:固定資産税評価額の0.1〜2%、借入額の0.1~0.4%
● 司法書士への報酬:1〜13万円程度
● 融資事務手数料:3〜5万円程度、借入額の1〜3%程度
● 物件調査手数料:6~8万円程度
● 固定資産税清算金:固定資産税評価額の6分の1×1.4%の日割り金額
● 仲介手数料:物件価格の3%+6万円程度
現金で支払いが求められる費用は、それぞれのどの程度なのかを把握しておけば、安心して資金計画を立てられるでしょう。
ローン完済時の年齢
住宅ローンを組む際には、現在の収入だけでなく、完済時の年齢も考慮に入れるのがポイントです。多くの金融機関では、ローンの完済時年齢を80歳前後に設定しています。そのため、定年退職後に収入が減少することを考慮しなければなりません。
たとえば、35歳で2,500万円のローンを35年で組んだ場合、完済時の年齢は70歳になります。仮に65歳の定年までは返済に問題がなくても、その後の5年間の収入減少に備えた計画を立てることが求められます。
返済期間の短縮や繰り上げ返済といった方法を活用し、定年後も無理なく返済できる計画を検討することが必要です。
まとめ
マイホームの購入を検討する際、年収倍率や返済負担率を考慮し、無理のない計画を立てることが重要です。また、住宅ローンの完済時年齢や頭金の準備、現金で支払わなければならない諸費用についても理解を深める必要があります。
群馬セキスイハイムでは、ファイナンシャルプランナーによるライフプラン診断を無料で受けられます。永く安心してお住まいいただける家づくりをお手伝いさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。